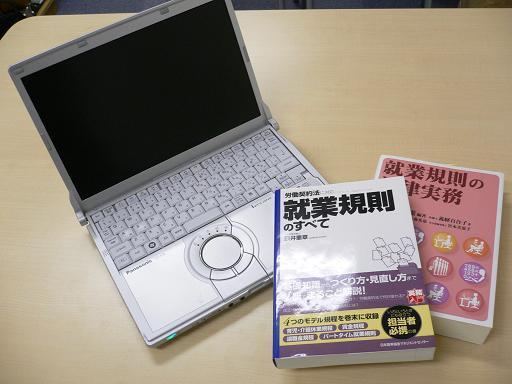企業経営の人にまつわるご相談なら
神戸元町労務管理サポート
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5-2-19-401
JR元町、地下鉄県庁前からJR元町徒歩2分、地下鉄元町徒歩2分
受付時間 | 午前9時から午後5時 |
|---|
休業日 | 土日、祝日、年末年始、夏休み |
|---|
※特別なご要望がございましたら土曜日対応も可
問題のある就業規則
1 総則、適用範囲
パートタイム労働者やアルバイトなどの非正規社員については正社員の就業規則は適用除外としておいて、別に定める規定を適用するとしているのが一般的です。
行政解釈では、このような場合の取り扱いとして、就業規則の本則において別個の就業規則の対象となる従業員に関する適用除外規定か委任規定を設けておくことが望ましいとされています。
解釈例規【一部の労働者に適用される別個の就業規則】
同一事業場において、労働基準法3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、この場合は、就業規則の本則において当該別個の就業規則の適用対象となる労働者に係る適用除外規定又は委任規定を設けることが望ましい。
なお、別個の就業規則を定めた場合は、当該二個以上の就業規則を合したものが法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条に気鋭する就業規則となるものではない。(昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)
以下の「問題のある規定」でも契約社員、嘱託については「別に定めるほか、この規則を社員に準じて適用する。」と定められています。しかし、このような表現では本則のどの部分が契約社員、嘱託に適用されるのか全く不明瞭です。ことあるごとに検討するというのでは労働条件が明らかになっているとはいえません。ことによっては、契約社員や嘱託から予想していない要求が出てこないともかぎりません。規定例1のように「ただし、別規則に定めのない事項は、本規則を適用する。」と適用範囲を明確にしておく必要があるでしょう。
問題のある規定
(適用範囲)
第○条 この規則は前条に定める社員について適用する。
2 契約社員は、別に定めるほか、この規則を社員に準じて適用する。
3 嘱託は、別に定めるほか、この規則を社員に準じて適用する。
4 パートタイマーについては別に定める.
就業規則規定例1
第○条(適用範囲)
この規則は、○○会社の従業員に適用する。
2 パートタイムの従業員及び嘱託その他必要ある者については、別に定めるところによる。ただし、別規則に定めのない事項は、本規則を適用する。
就業規則規定例2
(適用範囲)
第○条 この規則は、第○条の定めにより採用された社員に対して適用する。
2 第○条の定めにより、パートタイマーとして採用された社員については、別に定める「パートタイマー就業規則」を適用する。
2 労働条件の明示
就業規則規定例
第○条(労働条件の明示)
会社は、従業員との労働契約の締結に際して、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。 労働条件が明確にされていない場合、労働条件に関する事業主と労働者の理解のくい違いが生じ、トラブルを引き起こすおそれがあります。そのため、事業主の方には労働者を雇用する際、労働条件(賃金や労働時間など)を明確にし、労働者に対して書面によって明示する義務があります(労働基準法第15条)。
労働者と事業主との確かな信頼関係を築くために、しっかりとした労働契約を結びましょう。
就業規則規定例
第○条(労働条件の明示)
会社は、従業員との労働契約の締結に際して、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。
3 解雇事由
解雇の事由は労働基準法第89条により就業規則の絶対的必要記載事項になっています。平成15年の労基法改正により、絶対的必要記載事項「退職に関する事項」に「解雇の事由を含む」と明記されました。
そこで下記「問題のある規定例」にもみられるように解雇事由について列挙する必要があります。現在のところ就業規則に記載された解雇事由は限定列挙といって、定められた解雇事由でしか解雇できないとされていますので、規定内容については慎重に検討し、さらに最後に「その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき」のように一般条項を記載しておく必要があります。この規定をおくことによって限定的に列挙された解雇事由に相当するような事実についても解雇で対応することができることになります。
問題のある就業規則規定
第○条 (解雇)
社員が次の一に該当する場合は解雇する。
(1) 身体又は精神の障害により、職務に耐えられないと認められた場合。
(2) 勤務成績が著しく不良の場合。
(3) 前2号に規定する場合の他、その職に必要な的確性を欠く場合。
(4) 禁固以上の刑に処せられた場合。
(5) 会社の業務上の都合により、真にやむを得ない理由がある場合。
第○条(解雇の制限)
社員が業務上の傷病により、療養のため休業する期間並びに第43条の産前産後休暇の期間及びその後30日間は、解雇しない。ただし、業務上の傷病の場合において、療養開始後3年を経過して傷病が治らないときに、社員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む)はこの限りでない。
「問題のある事例」については(3)が一般条項にあたると考えられますが、1,2号の解雇事由に準ずるとしか書かれていませんので、一般条項としては極めて不十分です。せっかく一般条項を置くのですから、やはり各号の最後において、列挙された具体的な解雇事由を全て受けて「その他前各号に準する」としたほうが安全であると言えるでしょう。
実は解雇事由としては、下記に示すようにこれら以外に別の規定(解雇制限)の中でも「療養開始後3年を経過して傷病が治らないときに、社員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む)はこの限りでない。」と規定されています。この会社の就業規則では解雇事由が就業規則のいろいろな箇所で定められているようです。これでは、社員はどんなとき解雇されるのか不明瞭で不安です。労務担当者も就業規則をいつもまんべんなく読まなければ解雇事由を把握できません。一つの規定で解雇事由の全てがわかるようにする必要があります。
解雇事由の内容についても検討不十分と言えます。解雇事由として一般に挙げられるものは以下のようなものがあります。
1 勤務成績不良:無断欠勤が多い、欠勤・遅刻・早退が多い等
2 勤務態度不良:上司に反抗的、注意・業務命令に従わない、同僚と折り合わない・協力しない等
3 能力不足
4 私傷病による労務不能
5 社外非行:そのことにより、職場規律や職場風紀を乱した等の要件が必要
「問題のある事例」をみるとこれらの一般的な解雇事由の一部について列挙されていませんので、現在の事由との関連を考えながら書き加える必要があります。
また、実際の裁判になりますと、就業規則などの解雇事由に該当しているだけでなく、問題行動を指摘して是正するよう注意・指導をしたこと、本人に改善の意欲が認められないことなどを満たすことを求められます。そこでモデル就業規則のように「、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき」と書き加えておく必要があります。
4 通勤手当と割増賃金
かつては通勤は電車やバスを通勤手段とするのが一般的であり、通勤手当も定期代としてのみ規定され、そのように支払われていました。現在はマイカーを通勤手段と認め、キロ数に応じて通勤手当が支給されています。
規定例
通勤手当は、通勤距離が○km以上の者に対して月額○円までの範囲において、公共交通機関の1ヶ月定期代に相当する額を支給する。
さて、割増賃金の算定基礎に通勤手当は算入しなくてよいことになっています。 労働基準法第37条第4項によれば、割増賃金の算定基礎から除外できる賃金は(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)その他命令で定める賃金(以上限定列挙)とされています。
(3)のその他命令で定める賃金というのは、労働基準法施行規則第21条により、以下のように定められています。
1 別居手当 2 子女教育手当、3 住宅手当 4 臨時に支払われた賃金、5 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(以上限定列挙)
マイカーで通勤する労働者に対して通勤手当を支払うように制度を変更したときに、下記規定例のように合理的に金額を定め、賃金規程を変更していれば何等問題はありません。労働者の通勤距離や、通勤に実際に必要な費用に応じて算定される手当であれば、割増賃金の算定基礎から除外できる「通勤手当」となります。
就業規則、通勤手当規定例
第○条 通勤手当
1 通勤手当は、通勤距離が○km以上の者に対して月額○○○○円までの範囲において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
公共交通機関 当該交通機関の1ヶ月定期代
自動車(二輪を含む。以下同じ。)
通勤距離 片道2km~○km未満 月額 ○○○○円
通勤距離 片道○km~○km未満 月額 ○○○○円
通勤距離 片道○km~○km未満 月額 ○○○○円
2 公共交通機関と自動車の両方を使用する場合は、それぞれの合計額を支給する。
このような規定に変更しないままにしておき、さらに一律同じ金額をガソリン代として毎月定額で支払っているというような状態を続けていると、割増賃金の算定基礎に通勤手当も算入しなくてはならないようなことになりかねません。
というのは、次のような解釈例規があるからです。つまり、割増賃金の算定基礎に算入するか否かは手当の名称ではなく実質で判断するというものです。
【家族手当等の意義】
家族手当、通勤手当及び規則第21条に掲げる別居手当、子女教育手当は名称の如何にかかわらず実質によって取り扱うこと。(解釈例規 昭22.9.13発基17号)
さらに、次のような解釈例規があり、通勤距離や実際の費用に関係なく一定の金額を支給している場合は、一定の金額の部分については割増賃金の基礎に算入しなければならないとしています。
【通勤手当】解釈例規
問 一事業場において、実際距離に応じて通勤手当が支給されるが、最低300円は距離に拘わらず支給されるような場合においては実際距離によらない300円は基礎に算入するものと解する。但しこの際事業場が給与の均衡上除外された通勤手当の一部を算入することは妨げないものと解するが如何。
答 本文については見解のとおりである。但し書については家族手当、通勤手当等、割増賃金の基礎より除外しうるものを算入することは使用者の自由である。(解釈例規 昭23.2.20 基発297号)
5 代休と振替休日の違い
振替休日と代休は休日勤務を他の日で埋め合わせると言う点で類似しているので、両者を混同していることがよくあります。上記の問題のある規定例でも、これら二つの違いについて明確に理解して定めているとはいえません。この違いについては解釈例規があります。
問題のある就業規則規定
第○条(休日)
略
2 職務の都合でやむを得ない場合は、前項に定める休日に勤務を命ずるときがある。
3 前項の定めに休日に勤務した場合は、代休又は休日振替を与えることとする。ただし、代休日及び休日振替日は無給とする。
解釈例規【休日の振替と代休】
問 就業規則に、休日の振替を必要とする場合には休日を振り返ることができる旨の規定を設け、これによって所定の休日と所定の労働日を振り替えることができるか。
答 (1)就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。
(2) 前記1によることなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれに当たらないこと。(昭23.4.19 基収1387号 昭63.3.14 基発150号)
労働基準法35条で定められた休日であっても36協定の締結・届出を行うことにより、休日勤務をさせることは可能です。しかし、36協定という手続を行わなくても休日を振り替えるという方法で「休日だった日」に勤務させることができます。この休日を振り替えると言う方法が「振替休日」と呼ばれているものです。
「振替休日」とは、あらかじめ定められた休日を他の労働日と入れ替えて、休日を労働日とし、かわりの指定された日を休日とするものです。
「振替休日」を実施のための要件
1 就業規則等で「休日は毎週日曜日とする。ただし、業務の都合により会社は他の日に休日を振り替えることができる。」旨規定しておく。
2 振り返られた休日は当然、法定休日の範囲内でなければなりません。すなわち、「毎週少なくとも1回」あるいは「4週4日」の範囲内でなければならない。
就業規則規定例
第○条(休日)
略
2 法定休日は日曜日とする。
3 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。この場合においても4週間に4日の休日は確保する。
さらに、就業規則で振替休日と代休を明確に定めていても、実際の運用は代休として行っているにもかかわらず、それを振替休日と思い込んでいるという事例もあります。両者の違いをよく理解して運用しなければなりません。