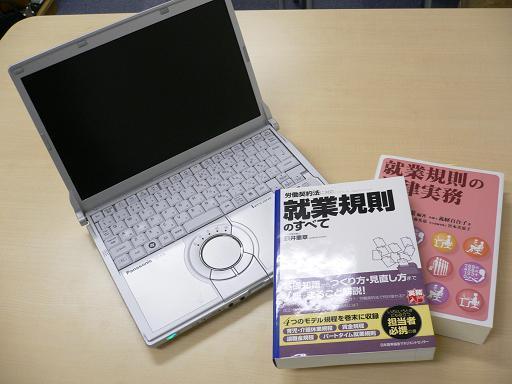企業経営の人にまつわるご相談なら
神戸元町労務管理サポート
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5-2-19-401
JR元町、地下鉄県庁前からJR元町徒歩2分、地下鉄元町徒歩2分
受付時間 | 午前9時から午後5時 |
|---|
休業日 | 土日、祝日、年末年始、夏休み |
|---|
※特別なご要望がございましたら土曜日対応も可
働き方改革関係法
改正労働基準法(施行期日:2019年4月1日)
残業時間の上限規制
労働基準法36条で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできない。
◎残業時間の上限は原則として月45時間、年360時間(1年単位の変形労働時間制採用の場合は、月42時間、年320時間)とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない(労基法36条3項、4項)。
◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、上限時間は
年720時間、複数月平均80時間(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。
月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。
原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヵ月までです。
上限規制の適用を猶予または除外する事業・業務があります。
| 自動車運転の業務(労基法140条) | 改正法施行後5年後に、上限規制が適用される。 ただし、適用後の上限時間は、年960時間とし、将来的な一般即の適用については引き続き検討される。 |
|---|---|
| 建設業(労基法139条) | 改正法施行後5年後に、上限規制が適用される。 ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均80時間以内・1ヵ月100時間未満の要件は適用されない。この点についても、将来的な一般即の適用について引き続き検討される。 |
| 医師(労基法141条) | 改正法施行後5年後に、上限規制が適用される。 ただし、具体的菜上限時間等については、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的在り方、労働時間の短縮等について検討し、結論を得るとされている。 |
| 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(労基法142条) | 改正法施行後5年後に、上限規制が適用される。 |
| 新技術・損商品等の研究開発業務(労基法36条11項) | 医師の面接指導(※)、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用されない。 ※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならない。 |
1 時間外・休日労働協定における協定事項
① 時間外・休日労働をさせることができる労働者の範囲・・・業務の種類と労働者数
② 対象期間:1年間の上限を適用する期間
事業が完了または業務が終了する期間が1年未満であっても対象期間は1年間としなければならない。
③ 時間外・休日労働をさせることができる具体的事由
④ 1日、1か月、1年間の延長時間または労働させることができる休日の日数
⑤ 時間外・休日労働協定の有効期間の定め(労基則17条1項1号)
⑥ 1年間の起算日(労基則17条1項2号)
⑦ 労基法36条6項2号(1か月100時間未満)および3号(1か月当たりの平均時間が80時間未満)に定める要件を満たすこと(労基則17条1項3号)
チェックボックスにチェックがないものは無効の協定となる。
⑧ 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置(労基則17条1項5号)
⑨ 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率(労基則17条1項6号)
⑩ 限度時間を超えて労働させる場合における手続き(労基則17条1項7号)
36協定の締結に当たり留意すべき事項(指針の内容)
※「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(平30.9.7 厚労告323号)
① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめること。(指針2条)
② 36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負う(指針3条)。
③ 「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(平13.12.12基発1063号)において、
・1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること
・1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていること
に留意しなければならない(指針3条)。
④ 労働時間を延長し、または休日に労働させることができる業務の種類については、業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしなければならない(指針4条)。
⑤ 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできない。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければならない。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めなければならない(指針5条)。
・限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならない。「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められない。
・時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、(1)1か月の時間外労働及び休日労働の時間、(2)1年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づけるように努めなければならない。
・限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければならない。
⑥ 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めなければならない(指針6条)。
(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間
⑦ 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めなかえればならない(指針7条)。
⑧ 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保しなければならない(指針8条)。
・限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければならない。
(1)医師による面接指導、(2)深夜業の回数制限、(3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)、(4)代償休日・特別な休暇の付与、(5)健康診断、(6) 連続休暇の取得、(7)心とからだの相談窓口の設置、(8)配置転換、(9)産業医による助言・指導や保健指導
⑨ 限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めなければならない(指第9条、附則3項)。
・限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければならない。また、月45時間・年360時間を超えて時間外労働を行う場合には、⑦の健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努めなければならない。
・限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければならない。
年5日の年次有給休暇の取得を、企業に義務付ける。
年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に対して、その付与日数うち年に5日について、労働者の希望を聞いた上で、希望を踏まえて時季指定をして取得させまければならない(労基法39条7項)
勤務時間インターバル制度の導入
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を努力義務とした(労働時間設定改善法2条1項)
労働時間設定改善法2条1項
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措を講ずるように努めなければならない。
産業医・産業保健機能の強化
必要な医学的知識に基づく誠実な職務遂行(安衛法13条3項)新設
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
産業医の権限の具体化(安衛則14の4第1)新設
産業医が安衛則14条1項各号に掲げる事項に係る職務をなし得るよう、事業者が産業医に付与すべき権限には、以下のアからウまでの事項に関する権限が含まれることが明確にされた。
[1]事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
[2]労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
[3]労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
知識・能力の維持向上(安衛則14条7項)
産業医は、安衛法13条1項に規定する労働者の健康管理等を行うに当たって必要な医学に関する知識および能力の維持向上に努めなければならない。